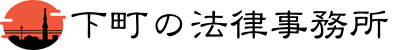龍光院から西へ15分程歩いた清澄二丁目に、深川稲荷神社があります。
布袋様をお祭りしている小さなお社で、宮司さんもおらず、町会で管理運営されています。
こじんまりとしてはおりますが、その歴史は寛永7年(1630年)まで遡ります。この付近の旧名は深川西大工町です。神社裏の小名木川は江戸初期から舟運で栄えましたので、この地域一帯に船大工が住み、造船、船の修理などをしていました。
そこから大工町の町名が生まれたといいます。
この小さなお社で、布袋様はさぞかし窮屈な思いをされているのではなかろうかと気になります。しかし、心配ご無用。さすがに布袋様は風雨に晒されながらも、その大度量でにこにこ笑顔を絶やしておりません。
布袋様の笑顔に見送られて最後の目的地深川神明宮に向かいます。高橋(たかばし)で小名木川を渡り、徒歩10分程で目的地に到着します。
まず立派な鳥居が目に飛び込んできます。
大阪摂津の人深川八郎右衛門が、この付近を埋立てて、深川村を造りました。
慶長元年(1596年)、徳川家康が鷹狩に来たとき、地名を尋ねると、住む人も少なく地名もないと答えたので、開拓者深川八郎右衛門の姓を村名にせよと命じ、以来深川村と称したと言われています。伊勢大神宮のご分霊を祀って創建した神社で、深川で一番古い神社です。関東大震災でも被害を受けなかったお社で、その際は当時の深川区議会がこの社殿で復興計画を立てたと言われています。
折口信夫が、関東大震災について「深川神明」と題して次のような歌を詠んでいます。
「焼け原のただ中に座て哭きにけり わがみ社はやけまさずけり」
こんな神社も東京大空襲の祭には全焼してしまいました。
さて拝殿です。神明造りなのでしょうか、立派な造りです。
ただ、敷地の相当部分を利用して幼稚園を経営している様子で、残念ながら荘厳な雰囲気とは些か縁遠い気がします。
さて肝心な寿老人です。
ご開帳の時期を外していましたのでお姿までは拝むことが出来ませんでした。他日を期したいと思います。