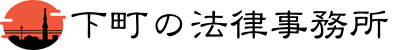ここで旧四つ木橋の虐殺現場から離れます。京成八広駅から京成曳舟駅へ、そこから東武曳舟駅まで歩き、同駅から東武電車に乗り換えてJR亀戸駅に向かいます。当時、今のJR亀戸駅北口の三井住友銀行亀戸支店辺りに亀戸警察署がありました。
(旧亀戸警察署跡地)
この署内も朝鮮人虐殺の現場となっていました。
元東亜日報社の雑誌「新東亜」の部長を務めた崔承萬は、1970(昭和45)年に出版した「極熊筆耕」において、亀戸警察に勤めていた羅丸山の目撃談として次のような事実を伝えています。
「私は86名の朝鮮人が銃と剣で切り殺されたのをこの目で見た。9月2日夜から9月3日午前までに亀戸警察練武場に収容された朝鮮人は300余名になっていた。そしてその日の午後1時ころに騎兵一個中隊がやってきて同警察署を監視していた。その時、田村という少尉の指揮のもとで軍人どもはみんな練武場になだれこんでくるや、三人ずつ呼び出しては練武場入り口で銃殺し始めた。すると指揮者は銃声が聞こえれば付近の人々が恐怖を覚えるだろうから、銃の代わりに剣で殺してしまえと命令した。それからは軍人どもは、一斉に剣を抜いて八三名を全部一緒に殺してしまった。この時妊娠していた女性も一人いた。その夫人の腹を裂くと腹の中から赤ん坊が出てきたが、赤ん坊が泣くのでその赤ン坊まで突き殺してしまった。殺された人の屍体は次の日の明け方二時、貨物自動車に乗せてどこかに運んで行った。その外の人達もみんなどうなったか知るよしもない。」(関東大震災朝鮮人虐殺の記録―西崎雅夫編111ページ)
亀戸警察署内での軍隊による朝鮮人虐殺が、警察の暗黙の了解の下で行なわれたことは、明らかです。
以上、旧四つ木橋、および、亀戸警察署内での朝鮮人虐殺の証言を見てきました。
朝鮮人虐殺の現場は、報告の挙がっているものだけでも千葉県船橋法典、埼玉県熊谷、本庄、群馬県藤岡、神奈川県新子安神奈川駅、神奈川鉄橋など関東一円70ヶ所以上に存在していました。
関東大震災当時、関東一円に居住していた朝鮮人は、朝鮮人虐殺研究の第一人者山田昭次立教大名誉教授の推定によれば、14,100人であり、その大部分は各地の工事現場などで肉体労働に従事する非組織的労働者でした。
そのような労働者が、大震災の最中に集団をなして一般住民に襲い掛かるなどあり得ないことは、常識的に考えればすぐに分かった筈です。
それなのに、何故旧四つ木橋での朝鮮人虐殺のような事件が関東一円で引き起こされてしまったのでしょうか?
吉村昭は、その著書「関東大震災」で、「大災害によって人々の大半が精神異常をきたしていた結果としか考えられない。そして、その異常心理から、各町村で朝鮮人来襲にそなえる自警団という組織が自然発生的に生まれたのだ。」(大震災178ページ)と記しています。精神異常としてしまっては、虐殺が行われてしまった原因が何であったのか探ることを諦めるに等しくなります。
虐殺の原因を探るためには、まず朝鮮人虐殺の実行部隊となった自警団結成のいきさつから知る必要があります。
1926(昭和元)年刊の西坂勝人著「神奈川県下の大震災火災と警察」は、「自警団員は、竹槍、刀剣や甚だしきは銃器を携帯して・・・不穏の状態を現してきたが、彼らは統率者なき烏合の衆なのでややもすれば無辜の民を殺傷し」と記しています。吉村昭の自警団自然発生説は、この文献がもとになっているのかもしれません。
しかし、自警団は、単なる「烏合の衆」だったのでしょうか?
神奈川県の鎌倉郡内で町村ごとに震災にどのように対応したかを調査した記録が、神奈川県史に載っています。その中の「自警団の組織如何」との質問には、中川村村長の「各部落に震災以前より組織し有りたるを以て、震災後に於ては之をして昼夜を問わず警備に一層努力しつつあり」、中和田村長の「各部落ごとに震災前より組織し震災後に於ては夜警其他一般に関し一層努力しつつあり」といった回答が載せられています。(渡辺延志「歴史認識日韓の溝」ちくま新書200ページ)
また、震災の年である1923年の横浜貿易新報(神奈川新聞の前身)2月27日の記事に「藤沢町西坂戸親交会自衛団では民衆警察の実をあげるために三月四日に盛大に発会式を実施することになっており、これは西坂・前藤沢警察署長の後援によるものである」とあり、4月27日の記事に「川崎警察署の太田署長が在郷軍人会、青年団と民衆警察事務の遂行について協議し、大いに了解」とあります。(渡辺延志「歴史認識日韓の溝」ちくま新書118~9ページ)
自警団は、震災前から設立されていたのです。
それなのに、先程の「神奈川県下の大震災火災と警察」は、何故わざわざこのような虚偽の事実を記したのでしょうか?この本の著者西坂勝人は、震災当時神奈川県警察部高等課長の職にあった人で、前藤沢警察署長でした。
西坂は、「地域の自警団が震災前に警察の主導で準備されており、その中心が在郷軍人と青年団であったこと」「自警団員が統率者なき烏合の衆でなかったこと」を当然知っていましたが、警察官僚の立場から、自警団の成立に警察が深くかかっていたことを隠さないといけないと考えて、このような記載をしたと考えられます。(渡辺延志「歴史認識日韓の溝」ちくま新書204~5ページ)
自警団が何故朝鮮人虐殺を行ってしまったのか?という当然の疑問に対し、吉村昭は、「日本の為政者も軍部もそして一般庶民も、日韓議定書の締結以来その合併までの経過が朝鮮国民の意思を完全に無視したものであることを十分知っていた。・・・祖国を奪われ過酷な労働を強いられている朝鮮人が、大災害に伴う混乱を利用して鬱積した憤りを日本人にたたきつける公算は十分にあると思えたのだ。」(大震災162~3ページ)と述べています。吉村昭は、「人々の大半が精神異常をきたしていた結果だ。」と述べながらも、朝鮮人虐殺の歴史的背景はさすがに押さえています。
前述の山田昭次立教大名誉教授も、当時の民衆意識の根底に朝鮮に対する優越意識・差別意識があったこと、1919年の三・一運動以後、朝鮮人は蔑視の対象であるとともに恐怖の対象となったことを指摘しています。「天下晴れての人殺しだから、豪気なもんでサア」(横浜市史編纂係「横浜市史」第5巻)といった横浜市民の言葉は、当時の民衆の優越意識の一端を示しています。
2008(平成20)年3月に発表された内閣府中央防災会議の「防災教訓の承継に関する専門調査会報告書」第2編第4章第2節「殺傷事件の発生」1「殺傷事件の概要(1)朝鮮人への迫害の項では、「当時、日本が朝鮮を支配し、その植民地支配に対する抵抗運動に直面して恐怖感を抱いていたこと」「無理解と民族的な差別」が背景にあったと指摘し、「歴史研究、あるいは民族の共存、共生のためには、これら要因について個別的な検討を深め、また反省することが必要である、と記しています。
これまで自警団が震災の前から警察の肝入りで組織され、その組織の構成員に在郷軍人会が加わっていたことを見てきました。以下では、自警団の有力な構成メンバーであった在郷軍人会の歴史を辿ってみたいと思います。
在郷軍人会は、1910(明治43)年、日露戦争の教訓から現役兵の常備部隊だけではこれからの戦争を遂行できないと痛感した陸軍の発案で、ドイツをモデルに結成され、1931(昭和6)年時点では260万人という陸軍の巨大な一組織として全国に張り巡らされていました。
しかも、この組織は、日清・日露以来の戦争・武力行使に参加した退役兵士たちを大量に組織していました。そのメンバーの韓国・韓国人との実戦経験は、自警団の行動に大きな影響力を持っていたと考えられます。彼らの実戦経験を振り返ってみます。 つづく
つづく